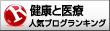親の判断力が低下すると、子の誰かが親の金銭管理をするケースが多いです。このとき、家族間の信頼関係が築けていないと、管理している子に対して、他のきょうだいが「好き勝手に使っているのではないか?」と疑念を抱くケースが往々にしてあります。

結論
「介護家計簿」を作る
きょうだい間では役割分担が必要です。その際、「お金の管理」は誰がどのようにするのかを、しっかり決めておくことが重要だといえます。その上で、使ったり立て替えたりした費用は、仕事の経費のように日付と明細を記して、レシートや領収書を残しましょう。私はこれを「介護家計簿」と呼んでいます。
親の家に備えておくなど、きょうだいがいつでも介護家計簿を見られるように、オープンにしておくのです。こうした作業を怠ると、「親のお金を搾取した」と修羅場になることがあります。早い段階での話し合いが欠かせません。
なかには、スマートフォンの家計簿アプリで記録し、きょうだいと共有している人もいます。領収書もスマホで撮影して保管するそうです。
解説
「死亡後」よりも「今の生活」に目を向けて
親のお金というものは、通常、亡くなれば子が相続することになります。そのため、「親自身が使い切ればいい」と考える子がいる一方で、「できるだけ残してほしい」と考える子もいます。
きょうだい間では、親の死亡後のことではなく、親の今の生活に目を向けながら、どういう介護をするかを話し合うことが大切です。その資金として、親の年金や預貯金の使い方を検討します。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」