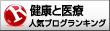「要介護」とは、日常生活において、自分一人で行うことが難しく、誰かの介護が必要な状態。例えば、お風呂の時に身体を自分で洗えないために入浴介助が必要など、他者の支援が必要な状態のことを指します。
それではその基準や申請について解説いたします。
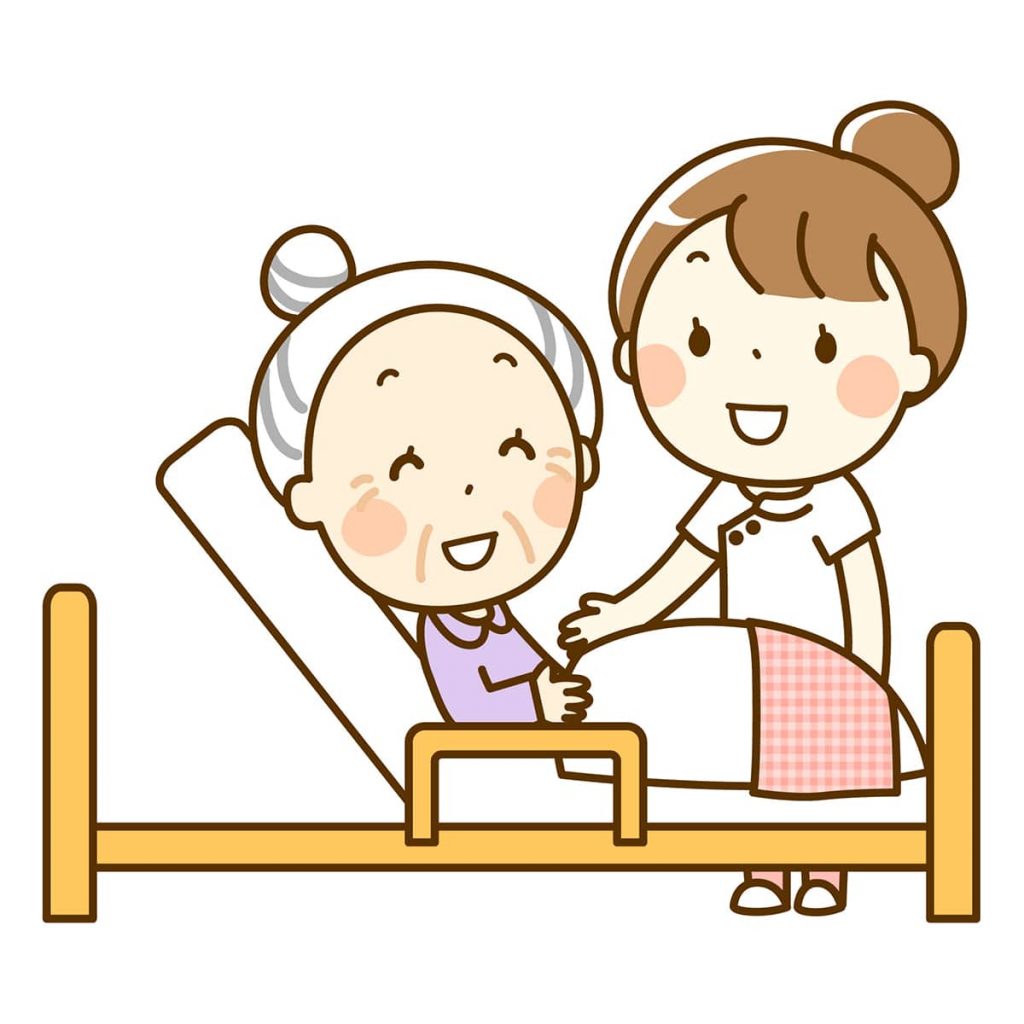
結論
要介護認定チェック項目
- 身体機能・起居動作
- 生活機能
- 認知機能
- 精神・行動障害
- 社会生活への適応
要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。介護サービスの必要度(どれ位、介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。
※参照:厚生労働省公式ページ
解説
「要介護認定」とは
65歳になると、医療保険の保険証と別に、1人に1枚の「介護保険被保険者証(保険証)」が市区町村から交付されます。しかし「介護保険被保険者証(保険証)」があれば、介護サービスを受けられると言うわけではありません。利用するためには認定を受ける必要があり、認定を受けるには、親の住んでいる地域の役所に、親本人や家族が申請する必要があります。入院中に申請することもできますし、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行申請を依頼することも可能です。
認定結果が出るまでの流れ
市区町村の窓口で要介護認定の申請を行うと、申請後に市区町村の職員などが親のもとを訪問し、聞き取り調査(認定調査)が行われます。また、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定および、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定。申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。認定結果は要支援1・2と要介護1〜5の7段階および「非該当」に分かれており、それぞれの要介護度に応じてサービスを利用できるようになります。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」