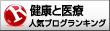日本の全世帯に占める高齢者のみの世帯(単身・夫婦)の割合は、2010年は20%でしたが、2025年には26%に増えると予想されています。さらに、2025年には認知症の人が730万人(高齢者の5人に1人)に増えると予測されています。ただ、高齢者の総数は、ピークを過ぎる(2042年と予測)と減少していくため、入居型の介護施設を多く整備すると、いずれ供給過多になります。

結論
国としては在宅介護を軸に整備を進めています。介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、
- 介護
- 介護予防
- 医療
- 生活支援
- 住まい
の5つの分野のサービスを、一体的に受けられる支援体制のことです。おおむね30分以内で駆けつけられる範囲(中学校区)に、必要なサービスが提供できる環境を目指しており、前項で紹介した各地の地域包括支援センターが調整役となります。
解説
地域密着サービスの連携
「地域包括ケアシステム」を実現するために、定期巡回・随時対応サービスをはじめ、小規模多機能型サービスなどが導入されました。また、近年続々と「サービス付き高齢者向け住宅」が創設されている背景でもあります。さらに、地域における介護や医療施設の連携強化も図られています。とはいえ、十分なシステムが構築されているわけではないので、自分たちのニーズに合う情報を入手し、サービスを選択する視点を持つことが必要です。
地域包括ケアシステムが目指す仕組み
- 医療が必要な高齢者や、重度の要介護高齢者についても、可能かかぎり在宅で生活できるよう支える仕組み
- 一人暮らし高齢者や、虚弱な長寿高齢者を在宅で支える仕組み
- 長寿化に伴い、増加が見込まれる「認知症高齢者」を、在宅で支える仕組み
- 入院しても、円滑に退院が可能となる仕組み
- 在宅で看取りができる仕組み
- 利用者や家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質)の確保ができる仕組み
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」