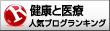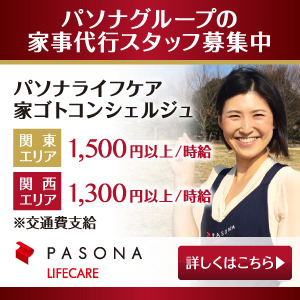結論
病院受診までに1年以上要する人は3割
「認知症の疑いがある親を、すぐ病院へ連れて行きましょう」と言われても、簡単ではありません。親は自分が認知症だと思っていないのに、説得して病院へ連れ出すのは至難の業です。また、子も親の認知症を受け入れられず、一過性のもの忘れだと思って、病院へ行こうとしません。最初の受診までにかかった期間は平均9・5か月で、1年以上を要した方が約3割、2年以上は約2割というデータもあります。だからといって、親をムリに病院へ連れ出すのはよくありません。親の自尊心を傷つけないことが大切です。
いやがる親を病院へ連れて行く工夫
お世話になっているかかりつけ医がいる場合は、風邪など他の病気で病院に行く機会と合わせて、認知症の相談をするのもオススメです。また、子である自分の通院時に、親に付き添ってもらって、そのまま認知症の診断を受けたという方もいます。もの忘れ外来によっては、家族のみの相談を受けつけている病院もあるので、まずはひとりで病院へ行って、医師と相談してみるのもいいでしょう。どんなに工夫しても、親を病院へ連れ出せない場合は、認知症初期集中支援チームや認知症コールセンターに連絡して、相談してみましょう。親を病院に連れて行くのではなく、医師に自宅まで来てもらう在宅医療を行っている病院を利用するという方法もあります。わが家は、市の無料健康診断があると言い、母を病院へ連れ出したところ、その場で認知症と診断されました。
いやがる親を病院へ連れて行く9つのコツ
- 市区町村の健康診断があるよと言って連れ出す
- いつもお世話になっているかかりつけ医に相談してみる
- 自分の通院に親もついてきてもらい、そのついでに受診する
- 親兄弟にも認知症診断を受けてもらい、一緒に受けてもらう
- 「この人の言うことなら聞く」という人から説得してもらう
- 認知症コールセンターに電話相談する
- 認知症初期集中支援チームに連絡すれば、訪問してくれる可能性もある
- 認知症の在宅医療を使ってみる
- 無理に連れ出そうとせず、次の機会を待つ
※誰よりも親自身が自分の異変に気づいています。無理に連れて行こうとせず、9つのコツを活用しましょう
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」