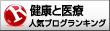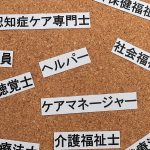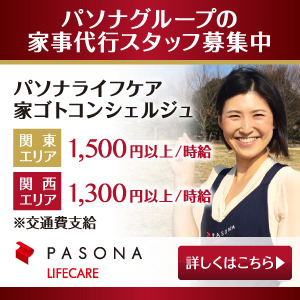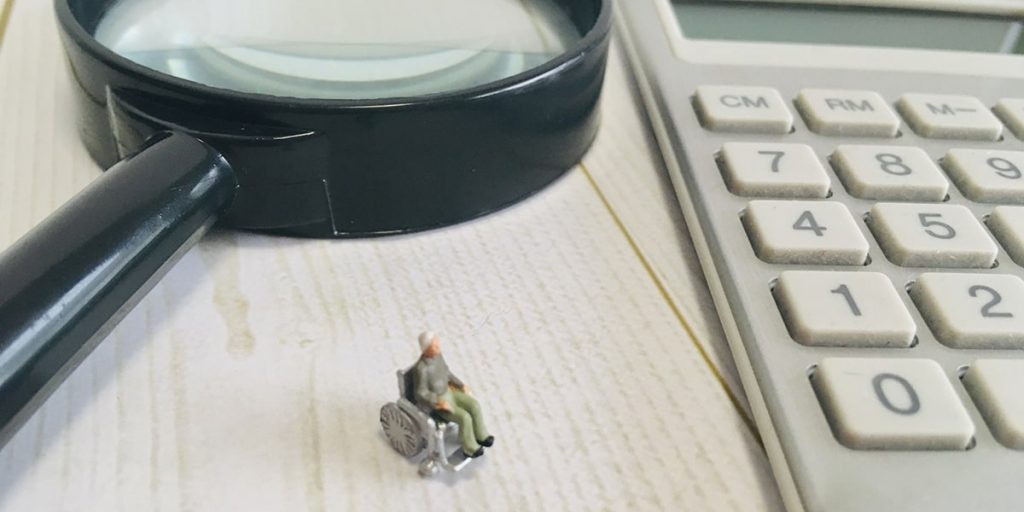
結論
要介護度ごとの支給限度額
介護保険サービス費用は、次表のとおり要介護度ごとに1か月の支給限度額が決まっています。さらに本人の所得と、世帯所得によって、自己負担額の割合が1割から3割まで変わります。要介護度が高いほうが支給限度額は増えるので、利用できるサービスは増えます。支給限度額を上回ってサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。また、福祉用具の購入・住宅改修については、要介護度にかかわらず、別途支給限度額が設けられており、福祉用具の購入は4月1日から1年間で年間10万円、住宅改修は1つの住宅につき20万円です。毎年6~7月頃に、市区町村から負担割合が記された負担割合証が交付され、親の負担割合がわかります。介護保険サービスを利用するときに、介護保険被保険者証と負担割合証の2枚を、サービス事業者や施設に提出する必要があります。
要介護度が高いからと言って得なわけではない
要介護度が高いほうが、支給限度額が増えるので、できるだけ高い介護度で認定されたほうがいいと考えがちです。しかし、要介護度が上がると、特養などの施設サービスや、デイサービス、ショートステイなどの基本料金も一緒に高くなるものもあります。その分、自己負担の金額も増えてしまうのです。支給限度額を超えるほど介護保険サービスを利用しているのであれば、今の要介護度が親と合っていないのかもしれません。その場合は、区分変更で経済的負担が減るかもしれないので、担当ケアマネに相談してみましょう。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」