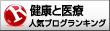結論
嫁や娘が介護する時代ではなくなった
一昔前までは、介護は女性の役割とされ、妻が夫の両親を、娘が実の両親の面倒をみるのは当たり前という時代もありました。厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2016年)によると、子の配偶者が介護をしている割合は、9・7%まで減少しています。もはや、自分の親の介護は妻に任せるのではなく、夫自身が面倒をみる時代に突入しています。背景には、少子化できょうだいが減り、自分以外に介護要員がいない、親と同居する世帯が減り、義理の両親との距離が遠いということもあります。わが家の場合、岩手の父、母、祖母の介護は、わたしの役割で、妻は全く介護をしていません。ただ、わたしが東京の家を空けることが多くなったので、その間の家事などは妻にお願いしています。実は、夫婦同時に遠距離介護を行っていた時期があり、妻は富山にいる自分の母を、わたしが岩手の家族を、それぞれ介護していました。残念ながらわたしは、義母の介護のサポートまで手は回りませんでしたが、それぞれの介護の知識を情報交換できるというメリットはありました。また、妻が東京の家を空けたときにやるべき家事をマスターしたので、わたしの家事力も大幅にアップしました。地域や世代によっては、まだまだ義理の娘(=嫁)が介護をするものと考えている方は多くいますし、自分たちの世代は嫁が介護していたから、下の世代も同じと考える人もいます。しかし、女性の社会進出が進み、共働き世帯が増え、2000年からは介護保険制度が始まり、家族だけで親を支える介護ではなくなっています。もはや女性だから、嫁、娘だからという理由だけで、介護を丸投げする時代ではなくなりました。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」