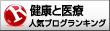「引きこもり」といえば、以前は若い世代の登校拒否などのイメージでした。しかし、その状態が長期化することにより、現在では中高年の引きこもり人口も相当な数にのぼると推測されています。また、一旦、就労した後に辞めて、引きこもる人も増加しています。
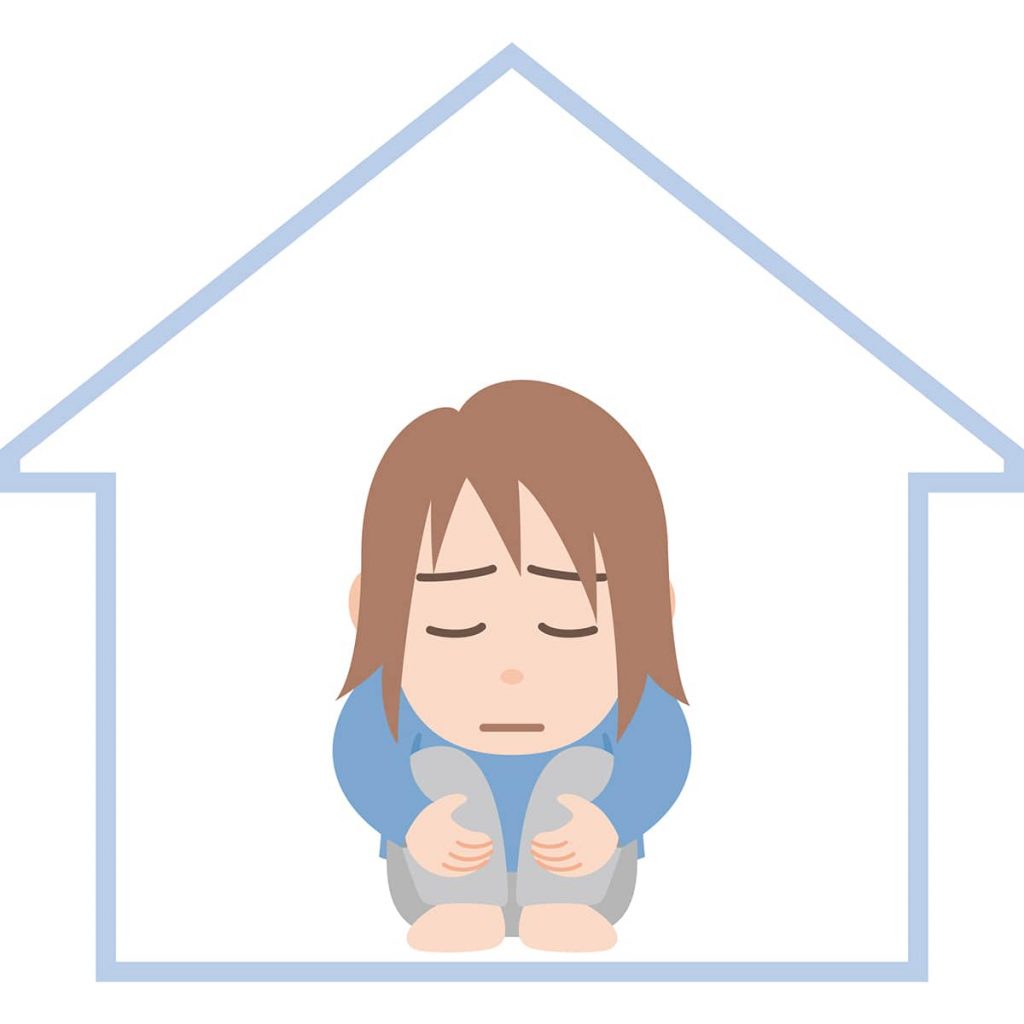
結論
抱え込まずに相談を
決して、珍しいことではないので、心配があれば地域包括支援センターなどで率直に相談してみましょう。同じ立場の人が悩みや情報を共有するための家族会もできています。また、国の「ひきこもり対策推進事業」による補助を受けて、各都道府県や一部自治体には「ひきこもり地域支援センター」が設置されています。
なかには、「家族だから」と、親のみならず、引きこもっているきょうだいのことも経済的に支援している子もいます。「きょうだいリスク」などという言葉も生まれていますが、特に、きょうだいの場合は年齢が近い分、先が長くなる可能性が高いです。背負いきれないのではないでしょうか。自身の結婚にも支障をきたしかねません。
引きこもっている人には、それなりの事情があり、責められるものではありません。だからといって、きょうだいに支援しきれるものでもないと思います。
きょうだいのことは福祉に任せる方向で検討を。親には施設に入ってもらい、きょうだいには生活保護を使ってもらうなど方法はあるので、家族だけで何とかしようとしないでください。
解説
「8050問題」とは
実際、親と別居する子から、「親元には、仕事をしていないシングルのきょうだいが暮らしている」という悩みを聞くことがしばしばあります。親の介護もなされていないケースがあるようです。
なかには、介護離職を経て、引きこもりになる子も。当初は、要介護になった親の世話をすることを目的に離職して親元に戻ったわけですが、行政などに必要な支援も求めず、孤立化し……。親が生きている間は親の年金がありますが、亡くなった後は、その者がどうやって食べていくかという問題が生じます。
また、経済的な問題だけでなく、一対一の介護は高齢者虐待を生みやすい構造にあるという懸念もあります。こうした事例が増加し、近年、「80代の親と50代の子」という意味で、「8050(はちまるごーまる)問題」と呼ばれるようになりました。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」