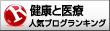親への関与を怠ると、看護や介護の質が低下することがあるようにも思います。医療、介護の現場とも人手不足。目を光らせる家族がいないと分かると、手抜きになるのではないでしょうか。

結論
「お任せします」は通らない
親が倒れ、入院・介護が必要になると、医師やケアマネジャーなどさまざまな人とともに親を支えることになります。そして、治療法の決断やサービスの契約などは、子どもたちの役割です。つまり、子どもはキーパーソンとなり、親の主治医やケアマネジャーとかかわる必要があるということです。基本、「契約」「決断」を第三者に「お任せ」はできません。どうしたいのか、当事者やその配偶者に判断力がない場合は、子が選択を迫られます。
解説
「ぽっと出症候群」にならない
「お任せします」とは逆のパターンですが、遠距離に暮らす子がたまにやって来て、親の主治医に治療法がどうだとか、こうだとか言うことがあるようです。確かに、離れて暮らしていると、心配ばかりが先に立ち、本やネットで仕入れた頭でっかちの情報で、現場をかき乱すことがあるのかもしれません。医師らは、こういう子を「ぽっと出症候群」と呼ぶそうです。
毎回は難しくても、たまに親の通院に付き添ったり、ケアマネジャーが親元を訪問する際に同席するなど、コミュニケーションの確保に努めたいものです。それは親の安心感にもつながるでしょう。ケアマネに早めに予定を伝えれば、日程調整をして会う時間を確保してもらえる場合もあります。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」