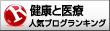親と別居のケースでは、親が入院、そして介護が必要になると「同居」を考えることがあります。通常、子が親元へ移り住む「Uターン」を選択するのは仕事などの事情で難しいため、自分の家やその近所への「呼び寄せ」を検討する必要があります。

結論
「遠距離介護」のメリット・デメリット
メリット
- 親子がそれぞれ住み慣れた土地に暮らせる
- 仕事や子育てなど、自分の生活のペースを維持できる
- 互いを思いやる気持ちを維持しやすい
- 介護保険のサービスが使いやすい(「別世帯」ということで、親の医療費、介護費が安くなることもある)
デメリット
- 「いざ」というときが不安
- 親の状況を把握しにくい
- 距離が遠くなるほど、通うための体力とお金が必要になる
- 周囲から「冷たい子」として見られる場面がある
解説
別居の親の「呼び寄せ」は難しい現実
多くの場合、親に提案しても「住み慣れた家がいい」と呼び寄せに応じません。
それは、もっともなことだと理解しましょう。住み慣れた場所だと友人や馴染みの店、風景、方言に囲まれています。呼び寄せても、子は日中仕事に出かけ、結局親は1人きりというパターンも。新たな環境に馴染むことは難しく、認知症などがある場合には悪化するケースも見られます。また、同居によって、介護保険などのサービス利用に制限が生じることもあります(2章13、6章4)。次図表でも分かるように、「子どもの家で介護してほしい」は少数です。
「遠距離介護」という選択肢
遠く離れて暮らしながら、親の介護をしている人は大勢います。本書で紹介している制度やサービスを活用すれば「遠距離介護」は可能です。
遠距離介護では、親も子もこれまで通りの生活を継続できます。当初は2つの地点で気持ちを切り替えることは難しいかもしれませんが、次第に慣れます。また、離れて暮らしているので、互いを思いやる気持ちを持続しやすく、優しくできる、などのメリットもあります。
親や自分の家族、親の担当ケアマネジャー、地域包括支援センターの職員などともじっくり話し合い、より良い方法を選択したいものです。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」